久しぶりにMeowbitを引っ張り出しました。
洗面所に時計が欲しかったのでMeowbitで時計ができないか試してみました。
コードはChatGPTさんに協力をいただいて作成。

アナログ+デジタル形式になりました。
Meowbitは時計機能が装備されていないので、正確な時間を刻むことができません。
微妙な時間のずれを調整する必要があります。
まあ、大体の時間を見るくらいであれば問題ないでしょう。
久しぶりにMeowbitを引っ張り出しました。
洗面所に時計が欲しかったのでMeowbitで時計ができないか試してみました。
コードはChatGPTさんに協力をいただいて作成。

アナログ+デジタル形式になりました。
Meowbitは時計機能が装備されていないので、正確な時間を刻むことができません。
微妙な時間のずれを調整する必要があります。
まあ、大体の時間を見るくらいであれば問題ないでしょう。
古いスマホをバイク用のカーナビがわりに使っています。
明るいところでは見にくいので、日除けカバーを作ってみました。

端材で適当にくっつけてあります。
バイクにつけるとこんな感じになりました。

劇的に改善したわけではありませんが、ちょっとはましになったと思います。
我が家の敷地境界にあぜ板で土留をしました。

大雨が降ると隣の敷地側に流れていくのを防ぐためです。
以前、畑に設置してあったあぜ板を流用します。

これで安心できます。
ついでに防草シートを設置して砂利も追加しようと思います。
森林の中に設置している雨量計です。
毎回落ち葉が貯まってしまい、うまく観測ができていないことが多いです。

こまめにチェックして掃除をするしかありません。
その負担を少しでも取り除くために、ちょっと加工をしました。
円筒形の筒を外すときに3箇所のボルトを外すのですが、結構面倒です。
この部分を蝶ネジに交換しました。


これでほんの少しですが、作業が楽になりました。
すべての雨量計を交換しようと思ったら、1箇所だけボルトの径が違ってました。
残念です。
また準備しておきます。
沢の流量観測を行っている場所です。
三角堰が設置してあるのですが、上流からの落ち葉などがすぐに貯まってしまいどうにもなりません。

こまめにメンテナンスできれば良いのですが、なかなか思うようにはいきません。
仕方がないので、堰の上流側にネットを設置しました。

焼肉用の金網を加工して置いただけです。
これだけでも効果があると思うのですが、これを設置しても今度はこのネットに落ち葉が詰まるだけなので、メンテナンスの必要性がなくなるわけではありません。
これ以上はどうしようもありませんので、しばらく様子を見ます。
水槽に接続されている流入パイプの流量を測定します。
タンクの下側に接続されているため、水没していて流量を測ることができません。

そのためホースを加工して流入するパイプに接続できるようにしておきます。
こいつを接続すれば、水がホースから流れてきますので、ここで流量を測定することができます。

何事も工夫次第でなんとかなります。
久しぶりに県内の現場に来ています。
現場では掘削工事の準備が始まっていました。
よく見ると地表には赤い土が分布しています。

ここは段丘面に当たる場所です。
どうやらこの辺りはかなり古い段丘面であり、風化がかなり進行しているものと思われます。
鉄分も多いのでしょうね。
地下水の性状はどんなものか興味があります。
でも雨に日には足を踏み入れたくないですね。
毎月通っている現場の田んぼの畦が荒らされていました。

おそらくイノシシの仕業と思われます。
幸い電柵がすでに張り巡らされており、電柵の内側は被害はない様子です。
最近は獣対策に労力をかなり取られているような気がします。
昨日6月21日は夏至でした。
1年で一番日が長くなる日でしたね。
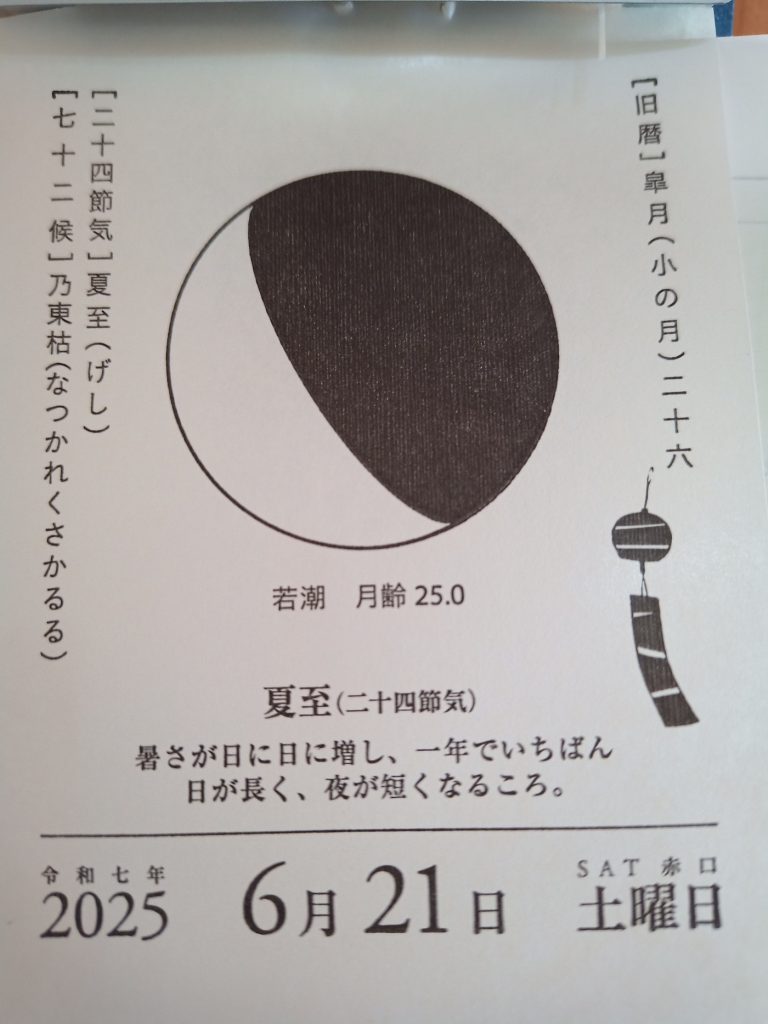
これからまだまだ暑い日が続きますが、陽が昇る時間はどんどん短くなっていきます。
真夏の炎天下でタブレットを使うことがあります。
熱暴走で使えなくなったこともあったので、対策を考えてみました。
ペルチェ素子を利用したモバイル用のクーラーです。

どれほど効果があるかわかりませんが、試す価値はありそうです。
水文調査で河川の流量観測をしています。
この猛暑の中、水辺で涼しげに見えますが、実際は胴長を履いていますので、それどころではありません。

サウナスーツ状態です。

空調服も意味をなしません。
15分が限界です。
不要になったら即、脱ぎ捨てます。
もはや夏の現場では必須品となりました空調服です。

私の装着している空調服はベスト型でフードもついています。
そして両サイドのファンが背中側よりももう少し脇腹に近い位置についています。

このおかげで車に乗った時も背中にファンが当たらずに快適に座ることができます。
これで今年の夏も乗り切りたいと思います。
海上の森センターから遊歩道を歩いた先にある物見の丘です。
いつも近くまでは来ているのですが、なかなかここまで来る機会がありませんでした。

木製の格子組が素晴らしいです。
もちろん上まで登ることができます。

爽やかな風が吹き抜けて気持ちが良い場所です。

できた当時はもっと遠方まで見渡せたと思うのですが、樹木の成長が著しいですね。
鬱蒼とした森になり始めていました。
手入れを怠れば一気に森に取り込まれてしまいそうです。
先週出かけていた山の現場です。
あちこちでクマはぎが見られました。
しかも新鮮なものばかり。




いったいどれだけのクマが存在しているのかと想像すると恐ろしくなります。
幸い、今年はまだ遭遇はしていません。
クマ鈴、クマ撃退スプレーは必須です。
家の裏の薪置き場にアシナガバチの巣が作られていました。
いつもは気にしていたのですが、見過ごしたようです。
すでに巣の形ができ始めて、女王蜂と働き蜂が2匹取り付いています。

アシナガバチなので、それほど脅威にはならないので場所よっては放置する時もあるのですが、この場所は人が通るところなので、除去させていただきます。
夕方、活動が収まった頃にハチジェットを吹き付けておきました。
ごめんなさい。
嫁さんの新しいスマホがやってきて、お払い箱になった古いスマホです。
バッテリーがへたってきていましたが、まだ現役として十分使えるレベルです。
もったいないので、バッテリーだけ交換しておくことにしました。

バッテリーを入手して、さっそくバラします。
最近の機種はほとんどが両面テープでくっついているので、ドライヤーで温めながら少しづつ剥がしていきます。

無事に空いたところで新しいバッテリーに入れ替えます。
あとは元に戻して完成です。
スマホカバーを新調しておけば、まだまだ十分に使えそうです。
バイクのナビ代わりに使おうかと考えています。
出前授業で子供たちに説明用の資料を作る際に、イメージ図が欲しい時がよくあります。
今までは、ネットで検索して著作権フリーの画像を使っていましたが、最近は生成AIを利用しています。
適当なキーワードを入れておけば、それっぽい画像を作ってくれます。
ちなみにボーリング調査のイメージをお願いしたら、こんなのが出てきました。
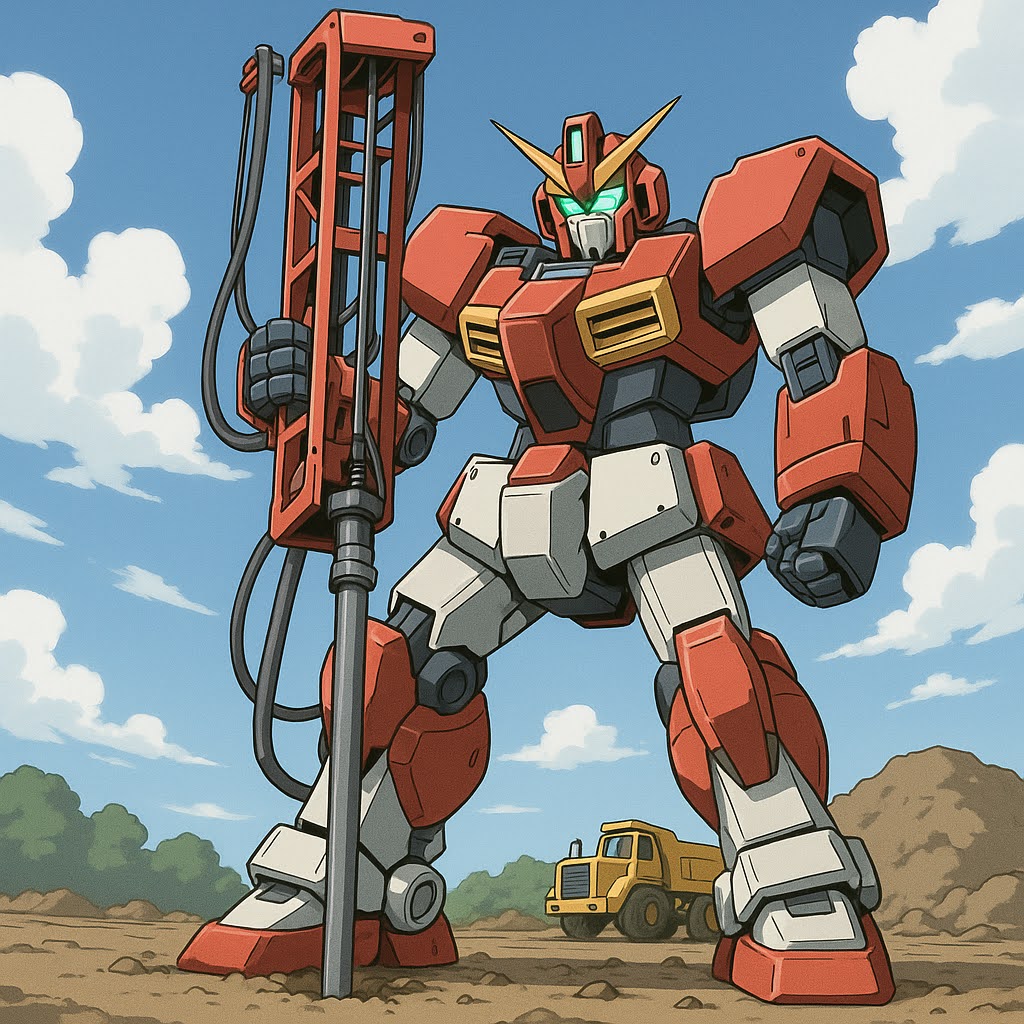
うーん、確かに私がキーワードにロボットアニメ風でと指示しましたが、これはちょっと使えないな。
というわけでボツとなりました。
普通の現場写真にしておきます。
先日の現場です。
お米所ではありますが、麦も収穫を迎えています。

一面に小麦色の景色が広がっています。
この地域は米の不作の影響はなさそうです。
お米の値段はしっかり上がっていましたが、、、
今週来ている現場はお米所でもあります。
田植えの終わった水田の水面に山が浮かび上がっていました。

いい感じです。
今年も実りの多いことを願います。
山の中の沢で簡易カメラを設置して流量観測をしています。
標尺をカメラでインターバル撮影しているのですが、時々珍しいものが映っていたりします。
まずはこちら。

写真中央下に魚影が映っていました。
イワナですかね。
ここには毎月通っていて作業しているのですが、全く気が付きませんでした。
いつもはどこかに隠れているのでしょうね。
続いてはこちら。

写真左下に得体のしれない生き物が映っています。
どうやらカエルのようです。
種類はよくわかりませんがヒキガエルかな。
こんなところには何もいないと思っていましたが、いろいろ生息しているみたいです。