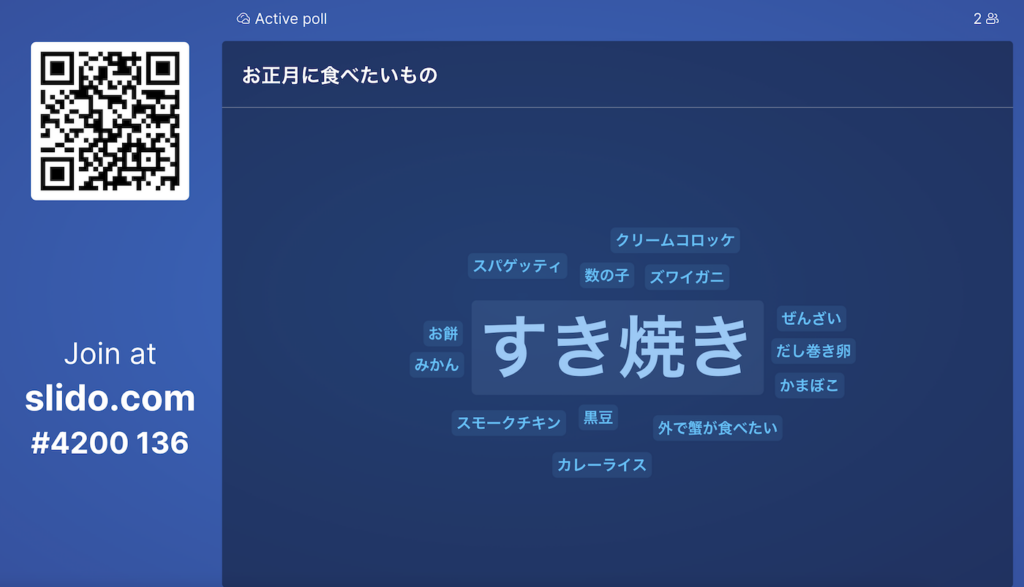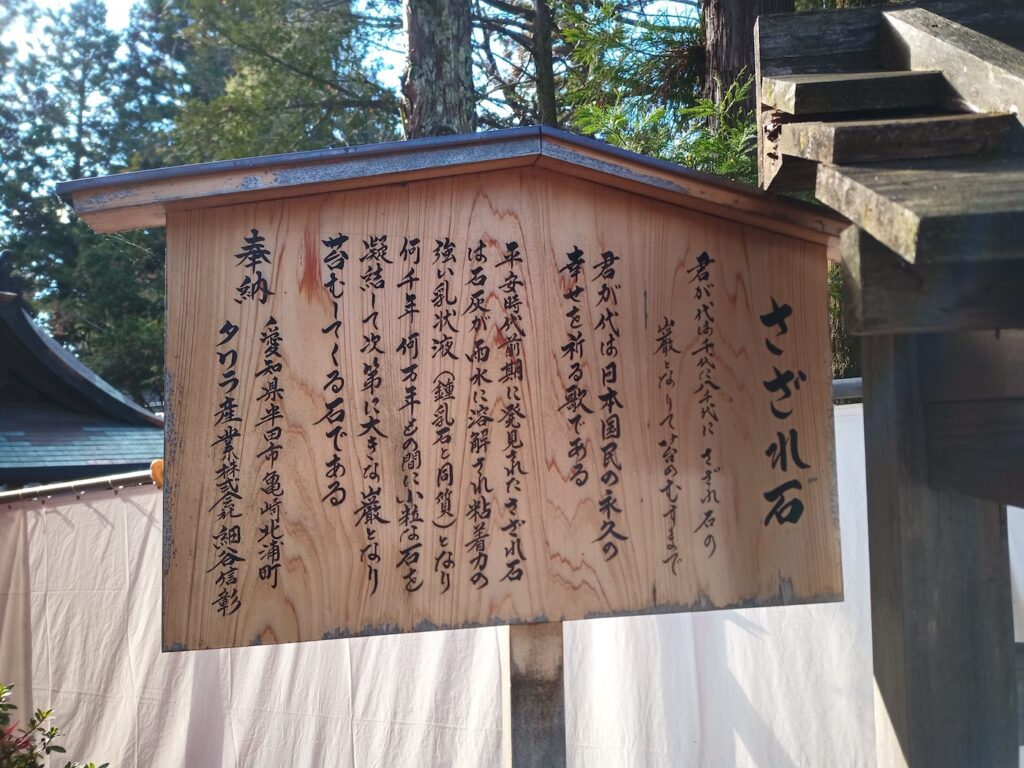パンク続きのエブリイです。
タイヤを純正の12インチから13インチに変更しているため、純正のスペアタイヤではサイズが異なります。

このためスペアタイヤを駆動軸にはめることはできません。
タイヤを入れ替えて対応することは可能ですが、山奥の不安定な場所ではかなり面倒です。
このためスペアタイヤも13インチにしたいところです。
ただ、そのままの状態ではサイズが異なるため、エブリイの下部に装着することができませんでした。

今までは倉庫に13インチの予備タイヤをストックしていたのですが、エブリイに常備するのが一番です。
なんとか13インチの予備タイヤが収まらないか試行錯誤してみました。
結果、スペアタイヤのキャリアの一部を無理やり曲げて、予備タイヤを裏返すことで装着できました。

かなり無理がありそうですが、落ちることはないでしょう。
これで現場でパンクしても怖くありません。
まあ、何もないのが一番ですが、、、