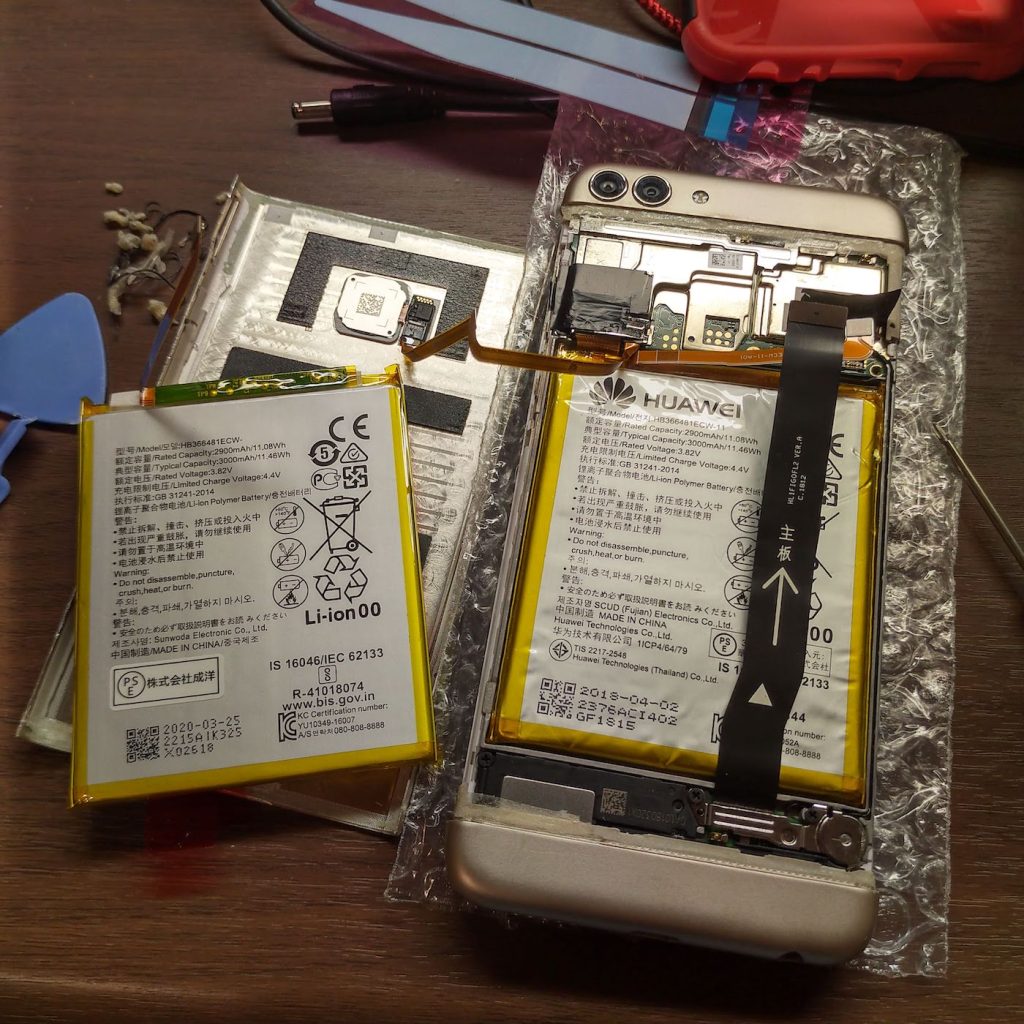裏庭の整備です。
先日までに大雑把な整地が完了しました。
本来は、ここに砂を敷いて丁寧にならしたいところですが、台風の影響で予定が立ちません。
このまま放置しておくと、また雑草が生え始めてしまいます。
仕方がないので、急遽防草シートだけ貼ることにします。
とりあえず、ホームセンターで防草シートを調達。

少し高めの良さそうなものを選んでみました。
これを四苦八苦しながら敷き詰めて完了。

下地に小石などが残ってしまっているので、この状態で放置しておくとシートが破れてしまいますが、仕方がありません。
ここから、この先まだまだやることはたくさんあるのですが、天気次第となってしまいました。
お祭りまでになんとかしたいところです。