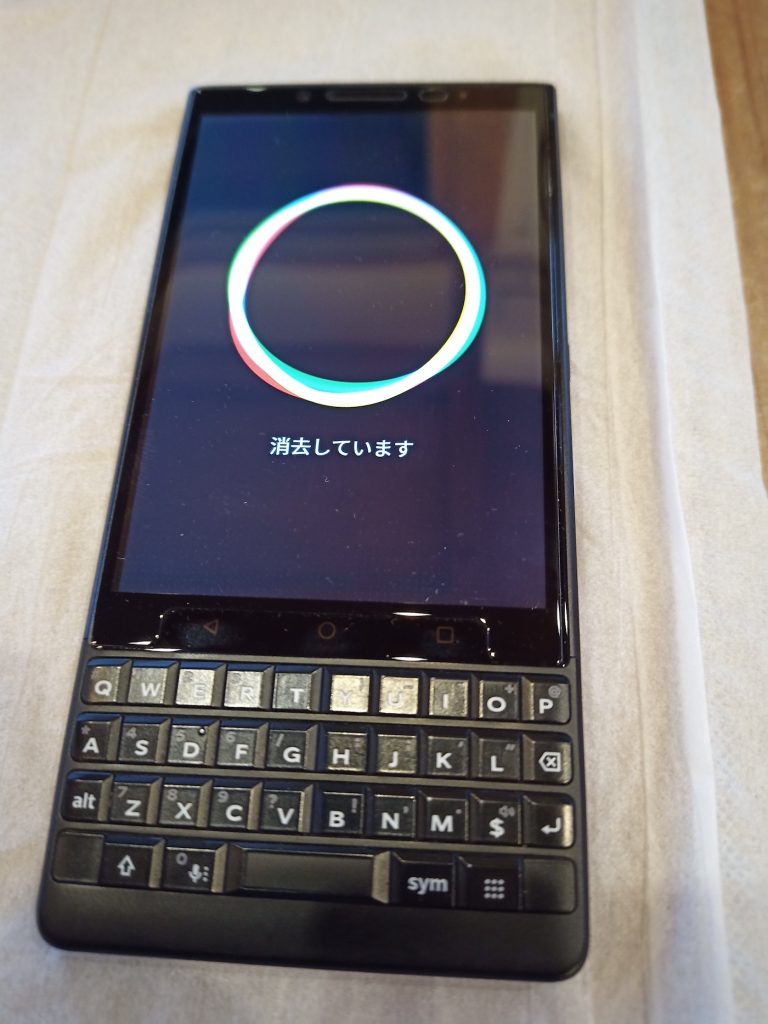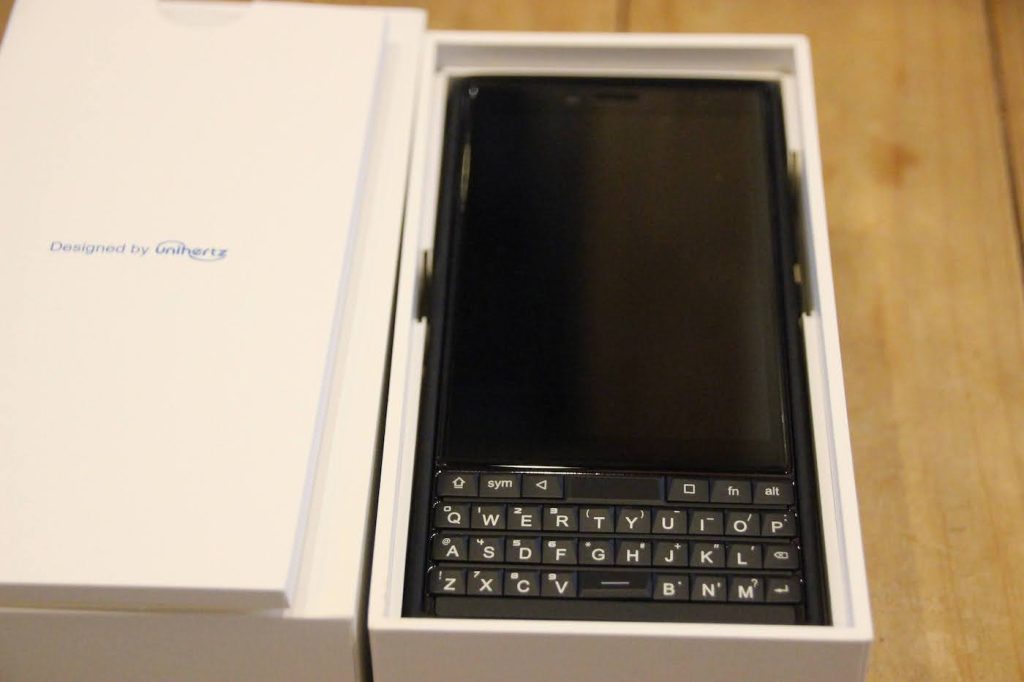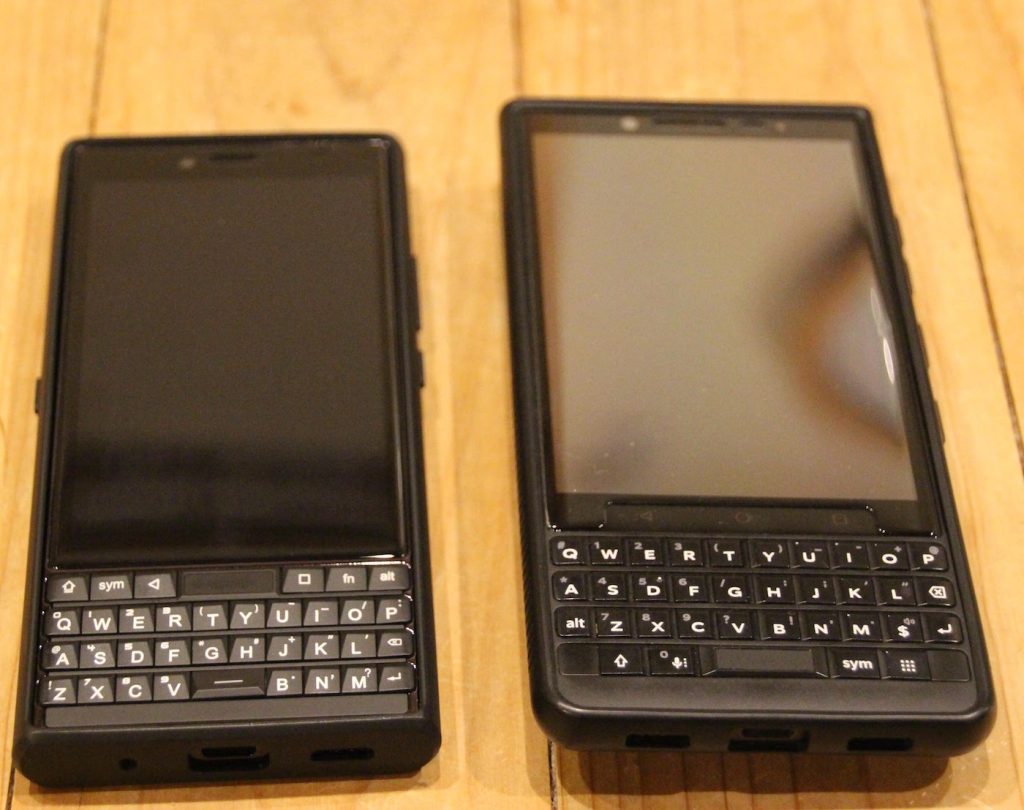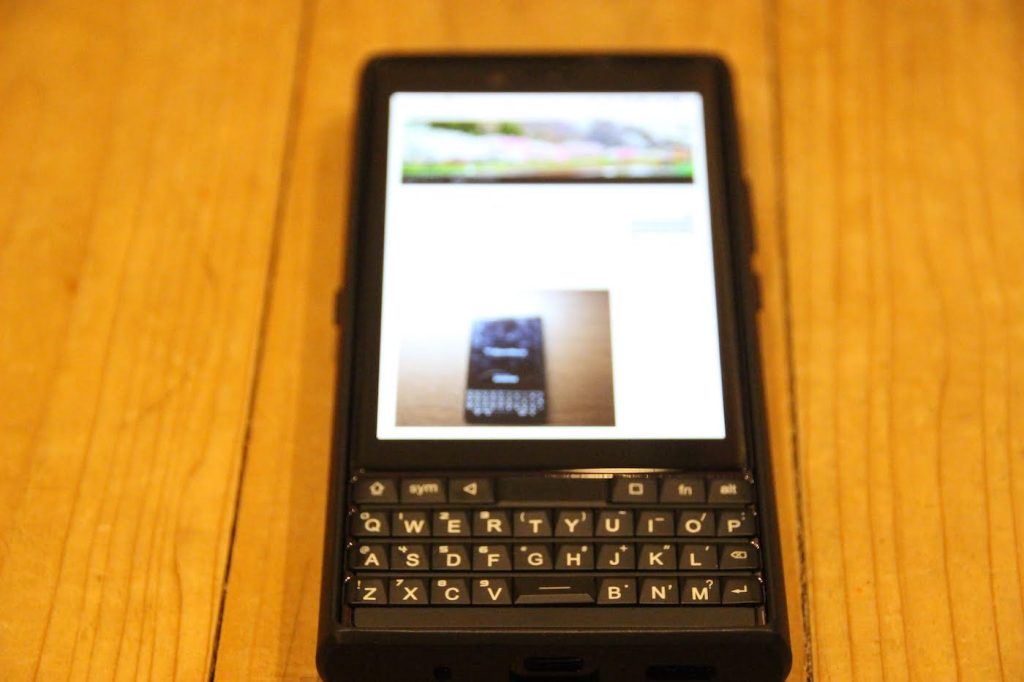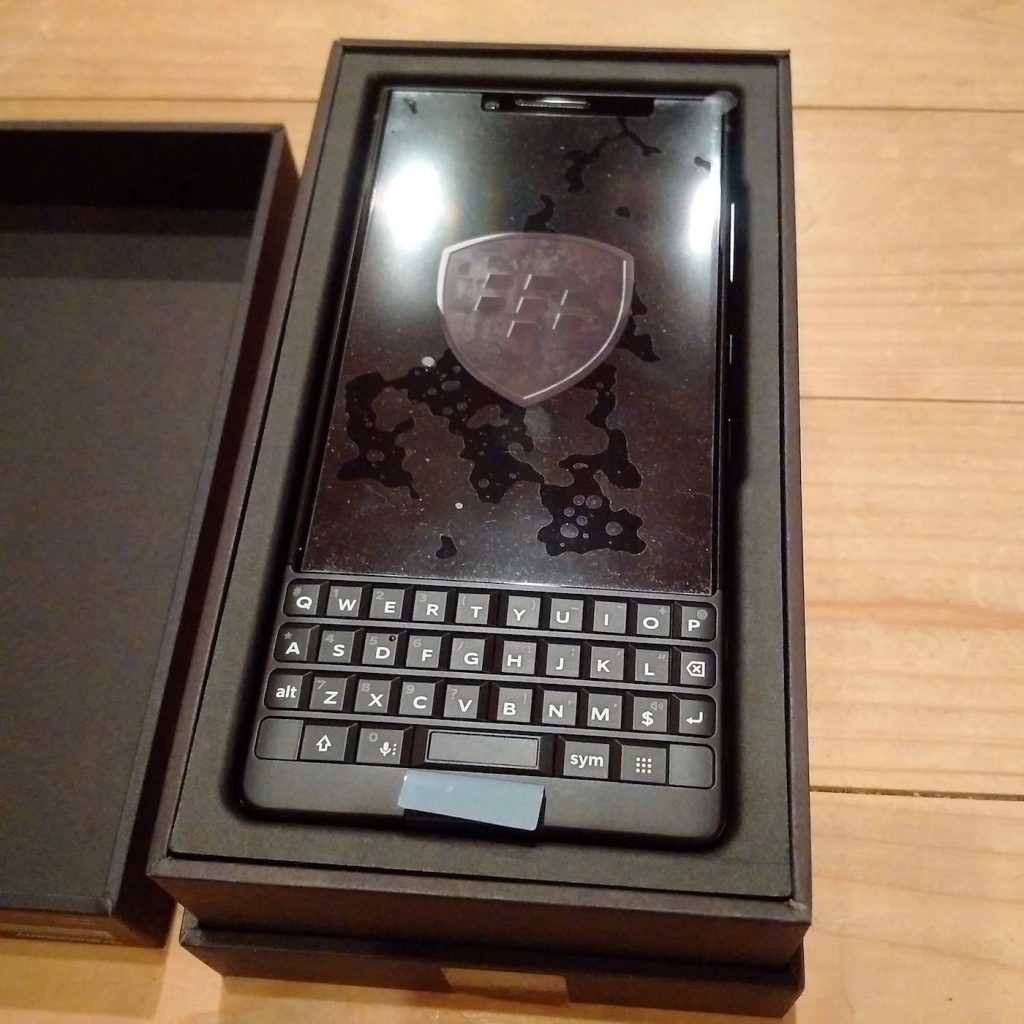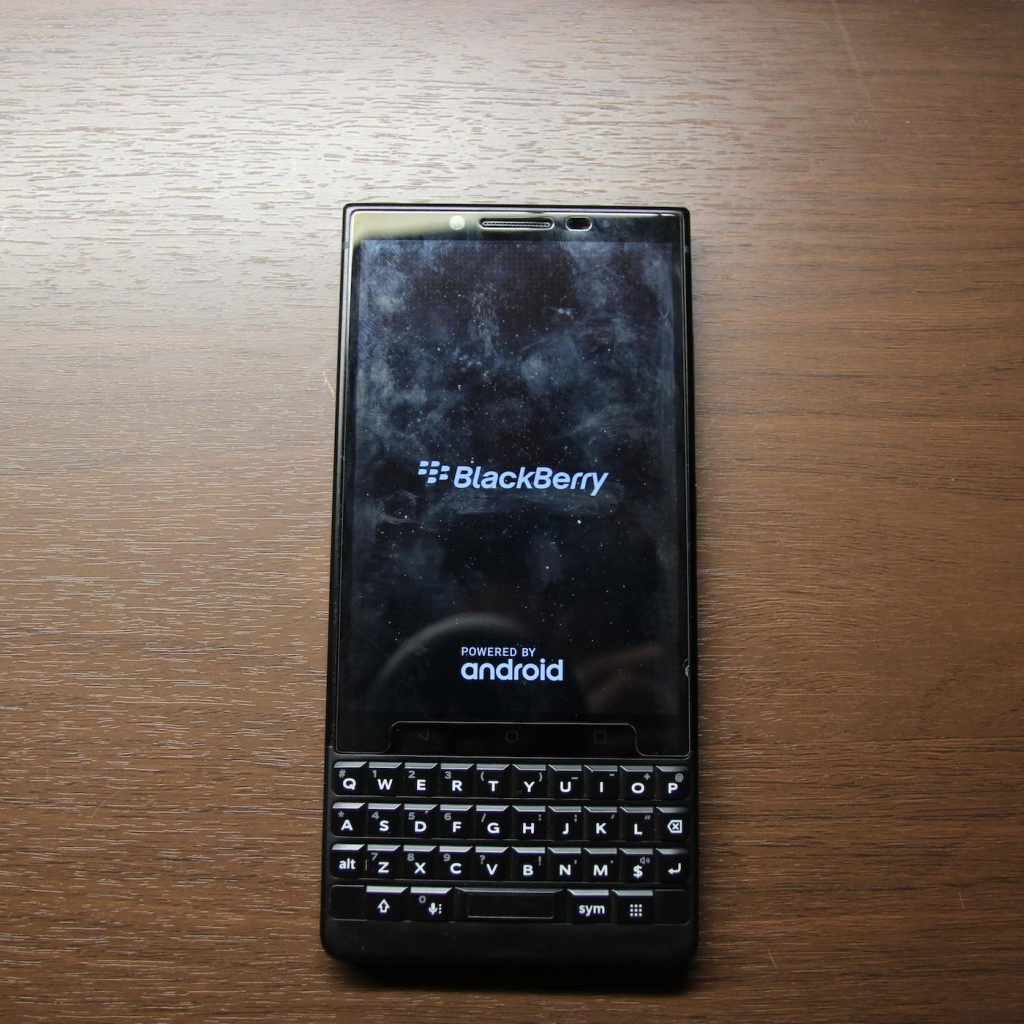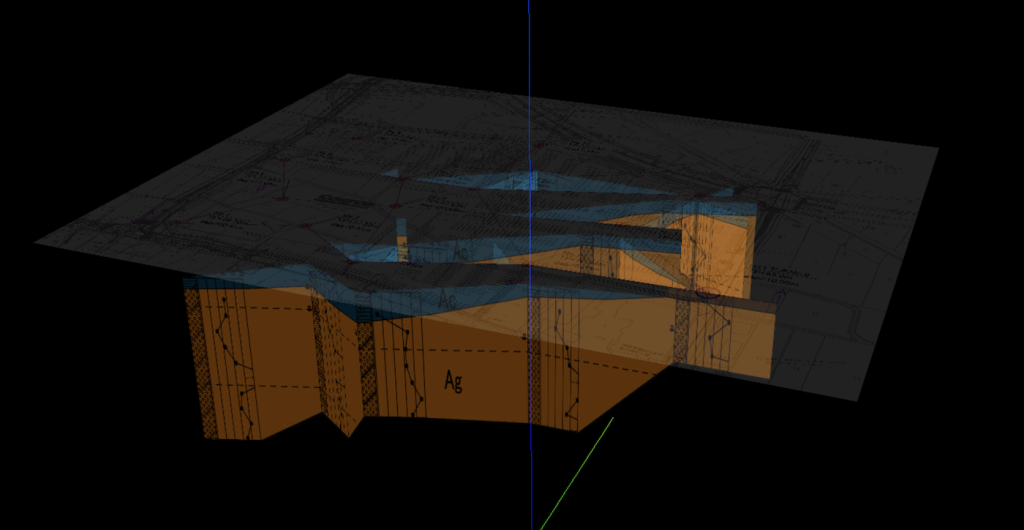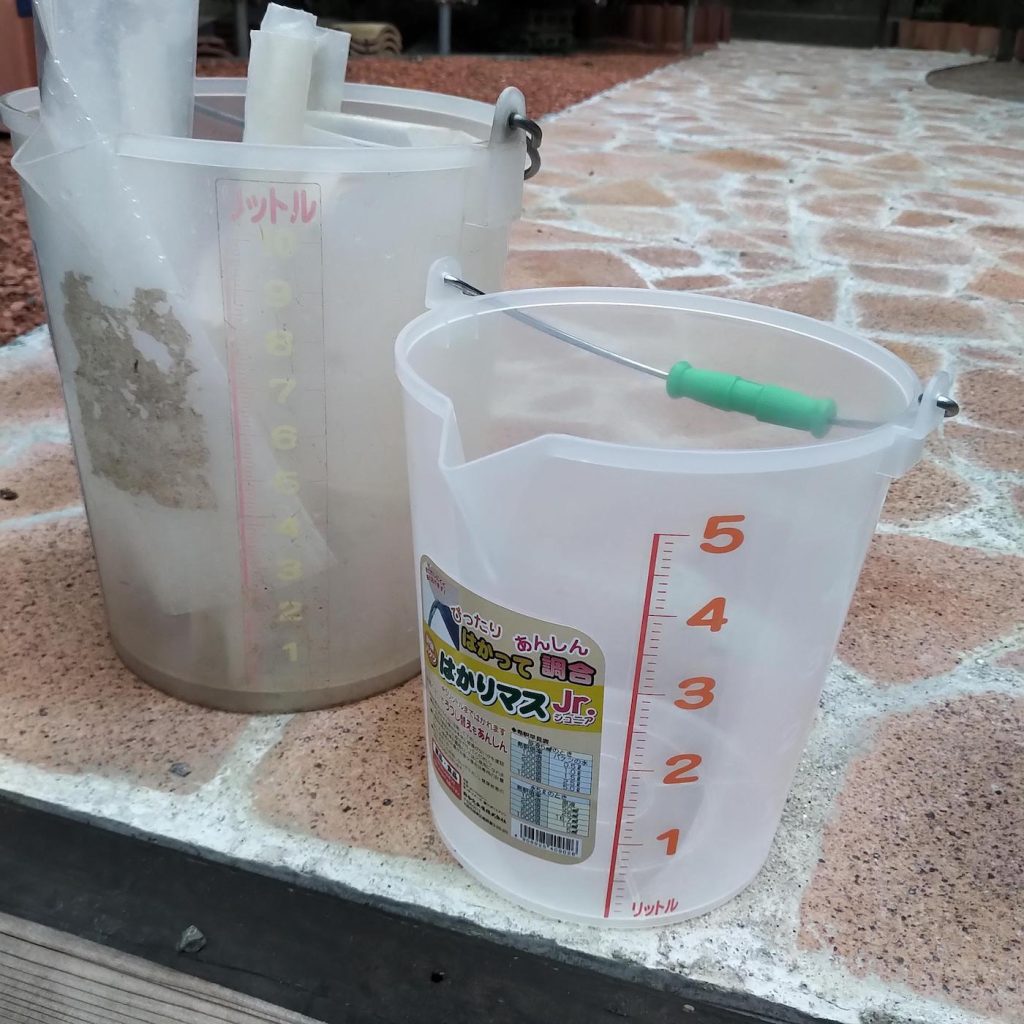もはや庭仕事のレベルを超えています。
毎年恒例となっている庭木の伐採作業です。
とりあえず斜面に斜めに伸びてしまったエノキを処理します。
10年くらい前に枝打ちをして可愛くしたはずですが、その姿はもはやありません。

電線にもかかるようになってしまいました。
とりあえず高枝切りノコギリで枝を処理しておきます。
上部にロープをかけて、下から引っ張れるようにしておきます。

方向を定めてチェーンソーで伐採します。
はい、伐採完了。

うまく畑に落ちてくれました。
お次は畑の奥で巨大化したモチノキ。
こいつは枝打ちだけで済まそうと思いましたが、よくみるとこのままでは倒れると電線にかかりそうでした。
ここで諦めて放置すれば、数年後にはさらに悪化することは目に見えていたので、こいつも伐採することにしました。

倒してから改めてみるとデカいです。
そんなわけで我が家の伐採作業は無事?完了。

まだ片付けが残っていますが、それはぼちぼちとやることにします。
こっちが伐採前。

こっちが伐採後。

リビングからの景色もずいぶんと明るくなりました。